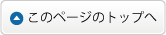危険物
ガソリンや灯油、軽油は「危険物」です
ガソリンや灯油、軽油は、私たちの生活にとってなくてはならない身近なものです。
しかし、これらは、消防法上の「危険物」に該当し、文字通り危険な物質として、その貯蔵や取扱いの方法について様々な規制がなされています。普段何気なく取扱っているこれらの危険物も、一歩貯蔵や取扱いの方法を誤れば、火災や爆発などの甚大な被害を及ぼす可能性があります。
ガソリンの特性について
性質
- 引火点はマイナス40℃以下。
- 自動車用ガソリンは、オレンジ色に着色している。
危険性
- 極めて引火しやすい。
- 揮発しやすく、蒸気は空気より約3~4倍重いので、低所に滞留しやすい。(風通しの悪い物置等に保管するのは危険です。)
- 流動など(容器を激しく揺らすなど)の際に静電気を発生しやすい。
火災予防
- 火気を近づけない。
- 火花を発する器具を使用しない。
保管方法
- 保管場所の通風と換気をよくする。
- 冷暗所に保管する。
- 容器は密栓する。(注入用ノズルや吸引ポンプを取り付けたままフタをしないで置いておくことは危険です。)
平成25年に京都府福知山市の花火大会会場で、ガソリンの取扱いに起因して、多数の死傷者を出す火災事故が発生しました。特に発電機の燃料として使用する場合、次のことに注意が必要です。
- ガソリンを取り扱っている周辺で、火気や火花を発する機械器具等を使用しない。
- 取扱いの際には、容器に設けられている圧力調整弁等で少しずつ減圧作業を行い、取扱説明書等に従って適正に行う。
- 発電機に注油する際は、必ず発電機を停止させてから行う。
灯油、軽油の特性について
性質
- 引火点は40℃以上(軽油は引火点45℃以上)。
- 灯油は無色、軽油は薄いグリーンに着色している。
危険性
- 加熱などにより液温が引火点以上になると、引火危険はガソリンとほぼ同様となる。(夏の暑い時期に風通しの悪い物置等、熱のこもる場所に保管するのは危険です。)
- 布などの繊維製品などにしみ込んだ状態では、空気との接触面積が大きくなるので、危険性は増大する。
- 揮発しやすく、蒸気は空気より約3~4倍重いので、低所に滞留しやすい。
- 流動など(容器を激しく揺らすなど)の際に静電気を発生しやすい。
火災予防
- 火気を近づけない。
- 火花を発する器具を使用しない。
保管方法
- 保管場所の通風と換気をよくする。
- 冷暗所に保管する。
- 容器は密栓する。(注入用ノズルや吸引ポンプを取り付けたままフタをしないで置いておくことは危険です。)
ガソリンの容器詰め替え販売について
ガソリンスタンド関係者の皆様へ
令和元年7月18日に京都府京都市において、35名が死亡、33名(容疑者1名含まず。)が負傷するという火災が発生しました。本火災は、ガソリンスタンドで購入したガソリンをまいて火をつけたとみられることから、ガソリンスタンドの関係者の皆様におかれましては、下記の留意事項を確認し、ご協力をお願いします。
- ガソリンの容器への詰め替え販売をする場合には、消防法令に適合した容器を用いて行うなど消防法令の遵守の徹底をお願いします。
- 購入者に対する身分証の確認や使用目的の問いかけと当該販売記録の作成等をお願いします。
- 不審者を発見したときの警察機関への通報体制について、改めて確認をお願いします。
ガソリンを購入される皆様へ
ガソリンは「危険物」として消防法に定められています。危険物は私たちの身近にある、とても便利なものですが、貯蔵・取扱いを間違えると、人命までも奪ってしまう大変おそろしい物質です。
ガソリンを容器詰め替え購入する場合は、ガソリンスタンド側から身分証の確認や使用目的の問いかけ等を行う場合があります。ガソリンの安全な取扱いのため、ご協力をお願いします。
震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱いについて
平成23年の東日本大震災や平成28年の熊本地震では、給油取扱所等の危険物施設が被災したことや、被災地への交通手段が寸断されたことなどから、ドラム缶や地下タンクから手動ポンプ等を用いた給油や、危険物施設以外の場所での一時的な危険物の貯蔵など平常とは異なる対応が必要となりました。
指定数量以上の危険物の貯蔵・取扱いは、市町村長等の許可を受けて設置された危険物施設以外の場所では行ってはならないことが消防法第10条第1項に定められていますが、同条第1項ただし書きにおいて、所轄消防長等の承認を受ければ、危険物施設以外の場所でも指定数量以上の危険物を、10日以内の期間に限って、貯蔵し、又は取り扱うことができるとされています。(仮貯蔵・仮取扱制度)
震災時等においては、臨時的な危険物の貯蔵・取扱いが必要となり、この仮貯蔵・仮取扱制度が数多く運用されることが予想されます。
震災時等において、危険物の仮貯蔵・仮取扱いが予想される事業所につきましては、「震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱いの安全対策に係るガイドライン」における安全対策を事前に計画いただくとともに、安全対策を講じる上で必要な資機材等をあらかじめ準備していただきますようお願いいたします。
※詳細な手続きについては、保安対策課までお問い合わせください。
製造所等の定期点検記録表
1 定期点検制度の概要
この制度は、特定の製造所等の所有者等に対し、製造所等の位置、構造、設備について定期的に点検を行い、その点検記録を作成し、これを法令で定められた期間保存する義務を課したものである。(法第14条の3の2)
2 定期点検が義務となる危険物施設
| 対象となる製造所等 | 対象施設 |
| 製造所 | 指定数量の倍数が10以上及び地下タンクを有するもの |
| 屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が150以上 |
| 屋外タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が200以上 |
| 屋外貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以上 |
| 地下タンク貯蔵所 | すべて |
| 移動タンク貯蔵所 | すべて |
| 給油取扱所 | 地下タンクを有するもの |
| 移送取扱所 | すべて |
| 一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以上及び地下タンクを有するもの |
| (備考)次の危険物施設は除く ◯ 鉱山保安法第19条第1項の規定による保安規程を定めているもの ◯ 火薬取締法第28条第1項の規定による危害予防規程を定めているもの ◯ 指定数量の倍数が30以下でかつ、引火点が40℃以上の第四類の危険物のみを容器に詰め替える一般取扱所(地下タンクを有するものを除く。) ◯ 移送取扱所のうち配管の延長が15mを超えるもの及び配管に係る最大常用圧力が0.95MPa以上で、かつ、配管の延長が7m以上15m以下のもの。 |
|
| No. | 定期点検記録表 | Excel | ||
| 1 | 別記1-1 | 製造所等定期点検記録表(積載式移動タンク貯蔵所除く) | Excel | PDF |
| 2 | 別記1-2 | 積載式移動タンク貯蔵所定期点検記録表 | Excel | PDF |
| 3 | 別記2 | 製造所・一般取扱所点検表 | Excel | PDF |
| 4 | 別記3-1 | 屋内貯蔵所(平家建)点検表 | Excel | PDF |
| 5 | 別記3-2 | 屋内貯蔵所(平家建以外)点検表 | Excel | PDF |
| 6 | 別記3-3 | 屋内貯蔵所(多用途部分を有するもの)点検表 | Excel | PDF |
| 7 | 別記4-1 | 屋外タンク貯蔵所(固定屋根式)点検表 | Excel | PDF |
| 8 | 別記4-2 | 屋外タンク貯蔵所(浮き屋根式)点検表 | Excel | PDF |
| 9 | 別記5 | 地下タンク貯蔵所点検表 | Excel | PDF |
| 10 | 別記6 | 移動タンク貯蔵所点検表 | Excel | PDF |
| 11 | 別記7 | 屋外貯蔵所点検表 | Excel | PDF |
| 12 | 別記8-1 | 給油取扱所(屋外)点検表 | Excel | PDF |
| 13 | 別記8-2 | 給油取扱所(屋内)点検表 | Excel | PDF |
| 14 | 別記8-3 | 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所(屋内)点検表 | Excel | PDF |
| 15 | 別記8-4 | 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所(屋内)点検表 | Excel | PDF |
| 16 | 別記9 | 移送取扱所点検表 | Excel | PDF |
| 17 | 別記10-1 | 一般取扱所(吹付塗装作業等)点検表 | Excel | PDF |
| 18 | 別記10-2 | 一般取扱所(焼き入れ作業等)点検表 | Excel | PDF |
| 19 | 別記10-3 | 一般取扱所(ボイラー・バーナー等による危険物の消費施設)点検表 | Excel | PDF |
| 20 | 別記10-4 | 一般取扱所(充てん施設)点検表 | Excel | PDF |
| 21 | 別記10-5 | 一般取扱所(詰め替え施設)点検表 | Excel | PDF |
| 22 | 別記10-6 | 一般取扱所(油圧装置等)点検表 | Excel | PDF |
| 23 | 別記11-1 | 屋内(外)消火栓設備点検表 | Excel | PDF |
| 24 | 別記11-2 | 水噴霧消火設備点検表 | Excel | PDF |
| 25 | 別記11-3 | 泡消火設備点検表 | Excel | PDF |
| 26 | 別記11-4 | 泡消火設備点検表 | Excel | PDF |
| 27 | 別記11-5 | ハロゲン化物消火設備点検表 | Excel | PDF |
| 28 | 別記11-6 | 粉末消火設備点検表 | Excel | PDF |
| 29 | 別記12 | 自動火災報知設備点検表 | Excel | PDF |
| 30 | 別記13 | 冷却用散水設備点検表 | Excel | PDF |
| 31 | 別記14 | 水幕設備点検表 | Excel | PDF |
| 32 | 別記15 | 地下タンク在庫量及び漏洩検知管点検表 | Excel | PDF |
お問い合わせ先
予防部保安対策課
電話 072-852-9910